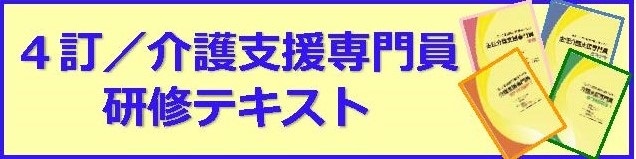分科会での演題発表者の募集は終了しました。
募集要項はこちら 抄録原稿様式はこちら
○応募資格
発表者は日本介護支援専門員協会の会員であること。
全国大会参加申し込みをしていること(発表者は別途、全国大会の参加申し込みを
お願いします。(※本大会は参集のみです))。
○発表件数
同一発表者の応募は、一つの分科会かつ、一つの応募に限らせていただきます。
なお同一事業所から複数の応募も歓迎いたします。
○費用
参加費・旅費・宿泊費・資料作成費・郵送費等は各自でご負担いただきます。
○発表、資料作成に関する注意点
①表題は、発表内容を適切に表現しているものを設定してください。
また抄録(資料)の文章表現、使用する概念や用語は適切なものをご使用ください。
②抄録(資料)に研究目的が明確になるように記載してください。
また研究・実践内容あるいは過程を記載してください。
③事例や調査に基づく研究発表の場合は、データ著作者にデータの使用と公表の
承諾を得ていることを抄録(資料)中に記述してください。 また発表者が所属する
機関の倫理委員会で承認された研究である場合は、その旨を抄録(資料)中に
記載してください。
この記述がない事例研究発表や調査研究発表は、採択されないことがあります。
④記述に際して、個人や地名、団体、学校等の特定につながる記述はお控えください。
この配慮が不十分な発表は採択されないことがあり、また採択された場合で
あっても修正を求めます。
⑤参考文献および引用文献は必ず抄録(資料)中に記載してください。
⑥提出前に今一度、以下ご確認をお願いいたします。
・原稿の作成方法、ページ設定が募集要項に適合しているか
・作成の注意点が募集要項に適合しているか
○演題発表までの流れ
エントリー 3月19日(水)~5月30日(金)
↓
抄録原稿提出 締切:6月30日(金)
↓
採用決定通知 予定:8月8日(金)
↓
発表データ提出 締切:9月30日(火)
↓
分科会発表
○エントリー方法
大会参加申し込みサイトMyページ内の専用フォームから必要事項を入力しエントリー
いただきます。
エントリー期間 令和7年3月19日(水) ~5月30日(金)
エントリー後、詳細事項について大会事務局よりメールにてご連絡します。
※原則としてメールでの対応(抄録原稿データの送付含む)とさせていただきます。
〇分科会テーマ及びキーワード
①演題発表希望分科会を次の各分科会テーマより選択して下さい。
但し、内容によっては、希望分科会以外の分科会にて発表していただくことも
ございます。
②演題発表内容におけるキーワードを各分科会キーワードより選択して下さい。
キーワードは、1つでも複数でも差し支えございません。
————————————————————————
【第1分科会】 家族(等への)支援(仕事と介護の両立支援等)
主旨
介護離職は日本の超高齢社会において深刻な問題となっています。依然として家族が介護すべきという価値観が根強く残っていることや、支援体制が整わず一人で抱え込む傾向があるということが介護離職の主な原因です。家族の介護を担うことで学業や将来の選択肢が制限される「ヤングケアラー」や、親の介護が長期化し自身の生活もままならなくなる「8050(9060)問題」が浮き彫りになっている状況もあります。
家族介護が抱える課題は、家族全体の生活だけでなく社会全体の持続可能性に影響を及ぼしています。こうした複雑な課題に対処するためには、地域社会全体での重層的な支援体制が不可欠であり、私たち介護支援専門員が果たす役割はますます重要度を増しています。専門的な知識と経験を活かし、家族が孤立せずに適切な支援を受けられるよう、地域の資源を活用した連携を進めていく必要があります。働きながら介護を担う人々への支援策が整備されることで、仕事と介護の両立を実現することが可能となり、社会全体を支えることに繋がっていきます。
このような取り組みを通じて、第1分科会では、誰もが安心して暮らせる社会を実現するための具体的な方法を模索し、共に考えます。
キーワード
①家族(等)への支援 ②仕事と介護の両立支援 ③重層的支援体制 ④生活困窮者の支援
⑤ヤングケアラー ⑥8050問題 ⑦孤立への支援 ⑧他制度との連携
⑨「等(支援者)」の定義づけ・関係の多様性への対応 ⑩社会資源の発掘・利活用 等
————————————————————————
【第2分科会】人材確保・育成
趣旨
介護支援専門員の高齢化・人材不足が叫ばれる中、介護支援専門員の平均年齢は53歳となり、4人に1人は60歳以上となっています。今後引退していく介護支援専門員が増えていく中で、事業所の人材確保は更に難しくなっていくものと思われます。令和6年度からケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会が発足し、引き続き「業務のあり方」「法定研修のあり方」等検討がなされています。
人材確保のポイントは「賃金」「労働環境」「やりがい」であり、多面的視点にたって対応することが重要です。またやりがいが削がれることがないように、現役世代の人材確保・育成とともに、次世代を担う未来の介護支援専門員を目指す人材の確保も重要な課題となります。
第2分科会では、効果的な人材確保・育成の実践事例と共に、次世代に向けた「介護支援専門員の未来像」について模索していきたいと考えています。
キーワード
①効果的な人材育成の方法(OffJT・OJT・SDS) ②法定内・外研修 ③スーパービジョン
④シャドウワーク対策 ⑤対人援助職としての学び ⑥働き方改革(労務管理)
⑦ハラスメント対策(カスタマーハラスメント等) ⑧職場環境分析
⑨介護支援専門員の魅力・未来像(やりがい) ⑩次世代へのメッセージ 等
————————————————————————
【第3分科会】 業務効率化とケアマネジメント
趣旨
1947年に4.54であった合計特殊出生率は2023年には1.20まで低下しています。日本の人口は減少を続け、とりわけ生産年齢人口の減少の加速が予測されます。その中で業務の効率化は介護業界のみならず日本の全産業的に求められる重要なミッションであると言えます。業務効率化の柱としてICT化の推進が推奨され、保険給付においても国の意思を感じることができます。しかし、実際の現場においてICT化の推進には、法人・事業所単位において濃淡を感じています。ではその背景には何があるのか?合わせて考えなければならないことは“業務効率化”の本質ではないか?ICT化が目的・目標となっていないか?
あくまでも“業務効率化”は手段でありICT化もまた業務効率化の手段です。では私たちは何のために業務効率化を行なうのか?第3分科会では業務効率化の具体的な事例に触れながらと業務効率化の本質について検討をしていきたいと考えています。
キーワード
①業務効率化の実践事例(現場での事例) ②ICT化推進に関する濃淡の背景
③介護支援専門員とAI・「人」だからこそできること
④業務効率化の本質 効率化の目的(質の向上・担保)、人としての役割
⑤ICT化からDX化へ(DX時代に備える) ⑥多職種連携
⑦介護情報基盤システム(Life、ケアプランデータ連携システム) ⑧Narrative Based Care
⑨生産性向上 等
————————————————————————
【第4分科会】地域共生社会(地域共生社会における介護支援専門員の実践と価値)
趣旨
人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、「地域包括ケアシステムの深化・推進」「自立支援・重度化防止に向けた対応」「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」「制度の安定性・持続可能性の確保」を基本的な視点として、介護報酬改定が行われました。「地域包括ケアシステムの深化・推進」において認知症の方や単身高齢者、医療ニーズが高い中重度の高齢者を含め、質の高いケアマネジメントや必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組を推進することが求められています。
生きづらさが身近なものとなり従来の社会保障のアプローチでは対応できない状況が生まれています。制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すもの「地域共生社会」の実現を目指します。
第4分科会では全国の皆さまと介護支援専門員の実践と価値をみつめたいと思います。
キーワード
①質の高い公正中立なケアマネジメント
②認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができる支援
③地域の実情に応じた柔軟な取組 ④地域共生社会における医療と介護の連携
⑤フレイル予防と地域づくり(住民・自治体による地域共生社会)
⑥在宅における医療ニーズへの対応 ⑦高齢者施設等における医療ニーズへの対応
⑧すべての世代にとって安心できる制度の構築を目指した支援
⑨地域づくりと介護支援専門員(地域にどう向き合うか)
⑩職能団体「日本介護支援専門員協会」実践報告、あゆみ 等
————————————————————————
○抄録原稿の作成と提出
事務局からの連絡を受け次第、抄録原稿の作成にとりかかって下さい。
※抄録原稿はエントリー前にも作成できますが、その際には指定様式に沿って作成
してください。
※指定様式は、全国大会専用ホームページ上からダウンロードできます。(リンク)
抄録原稿が完成しましたら、下記メールアドレスに抄録原稿を送付してください。
somuka@jcma.or.jp (日本介護支援専門員協会 事務局)
必ずメールのタイトルに【全国大会分科会原稿】と記載をお願いいたします。
【抄録原稿提出締切日 : 令和7年6月30日(金)】
○抄録原稿の作成方法(様式はこちら(リンク))
(1)用紙大きさ及び使用枚数
A4(縦)1枚で作成してください
(2)様式の基本設定
MicrosoftWordで、以下の設定にて入力して下さい
<設定>
・余白上70mm 下20mm 左20mm 右20mm
※上余白部分には、別途、見出し(タイトル、氏名、所属先など)が入ります。
・印刷の向き縦
・文字方向横書き
・文字数及び行数23字32行 2列(2段組)
・フォント MS明朝10.5ポイント
(3)作成上の注意点
①エントリー時には、演題タイトル、キーワード、演題発表者の氏名・所属支部名
(都道府県名)・所属先事業所名、共同研究者の氏名・所属先事業所名を
記入して下さい。抄録集に記載します。
②副題には前後に「〜」をつけてください。
③抄録原稿用紙の枠内に収めてください。
④発表する研究や取組みが、調査研究中または継続中で、完了していなくても
構いません。
(4)提出にあたっての留意事項
①演題発表の抄録は、大会誌に掲載し、参加者に配布いたします。
発表者は必ず作成方法に従い、提出下さいますようお願いいたします。
②事前に発表者の責任で制度確認を必ず行って下さい。
③提出いただいた抄録原稿は返却いたしません。
○査読基準について
提出いただいた抄録原稿は査読を行います。査読基準は以下の通りです。
査読基準11点以上を採択し、10点以下の場合は指摘事項を修正の上、再査読し11点以上を
採択とします。(10点以下の場合は、別紙の修正意見対応表をご提出いただきます。)
≪査読基準≫
1.表題は内容を適切に表現しているか
2.文章表現は適切であるか
3.図表は本文と照合して適切であるか
4.使用されている概念、用語は適切であるか
5.研究目的は明確であるか
6.研究・実践内容あるいは過程が示されているか
7.当該施設の管理者等からデータ使用と公表の承諾を得ているか
8.対象者からの承諾、個人が特定されない配慮、不利益が生じない配慮がされているか
9.抄録原稿の作成方法 ページ設定が募集要項に適合しているか
10.作成の注意点が募集要項に適合しているか
11.参考文献 引用文献が示されているか
以上全ての基準を「A 良い」「B 一部修正」「C 不適切」「非該当」で評価します。
動画「全国大会演題発表について~研究と査読基準~」を必ずご確認ください。
○採用決定通知
抄録原稿を査読し、実行委員会にて採択の要否を決定し、結果をメールでお知らせします。
採択決定通知 最終連絡日:令和7年8月8日(金)
○事前打合せ等、詳細について
演題発表の事前打合せの日時等につきましては、大会事務局より発表者へ後日、詳細を
連絡いたします。