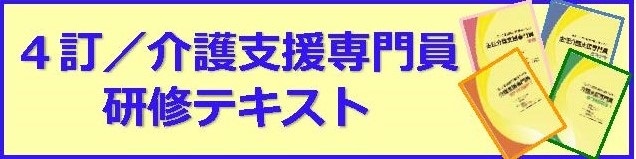平成29年7月5日に第142回社会保障審議会介護給付費分科会が開催されました。
当協会からの選出委員として、小原秀和(おばらひでかず)副会長が出席し、今回は訪問介護及び訪問入浴介護、訪問看護、共生型サービスの3つの議題について議論されました。
生活援助を中心に訪問介護を行う場合の人員基準及び報酬について、要介護者に対する生活援助の意義を踏まえた考え方や、身体介護も含めた訪問介護の報酬のあり方をどう考えるか-等が論点として示されました。この論点については、財務省が本年6月27日に公表した予算執行調査のうち、生活援助のみの利用状況を見た結果、月31回以上の利用者が6,626人で、月100回超えるケースもあるとのデータから、一定の回数を超える生活援助サービスを行う場合には地域ケア会議等におけるケアプランの検証を要件とするなど適切な利用の徹底を図るべきといったことが、財務省が考える改革の方向性(案)として打ち出された背景があります。
小原副会長は、この議題について次の発言をしました。
「生活援助のみの利用状況については、この利用者が集合住宅等に居住するのか、あるいは在宅での利用なのかといった状況によっても違いが出るし、なぜそのようなサービス利用状況になるのかも見る必要がある。財務省の指摘は、生活援助が中心となるケースと、定期巡回・随時対応型の対象像が異なることや、月当たりの基本報酬が定められている定期巡回・随時対応型の平均値と、生活援助の最大値との比較であり、データの妥当性があるのか疑問に感じる。その上で、このような特殊なサービス利用形態にならざるを得ないケースについては、充分に検討していく必要があり、様々なサービス利用のパターンがあってこそ、在宅生活が継続できるとうい側面もあるのではないか。
また、要介護高齢者等の個人が直面する暮らしにくさ、生活課題に対して、最低限必要な生活を継続するために活用する支援としての生活援助と家事代行サービスを比較するのは違和感がある。生活援助の場合は、居宅介護サービス計画に応じた訪問介護計画の作成や実施の際の声掛け、安否確認、様々な連絡調整等の附帯する業務も必要になる。生活援助の意義・必要性については、とても適切とは言えない生活環境にある利用者を支援することは少なくない実情がある。例えば、清潔な生活環境が担保できず、また不適切な食品の摂取、水分の不足、重要な薬の飲み忘れなどが頻回にあれば、容易に健康状態や生活状況の悪化につながることは、想像に易い。この辺りを自立支援と絡めて考えていかなければならない。」
時間の関係上、この日の議題として予定されていた「居宅介護支援」は次回に延期となりました。
※議論の詳細は、後日配信するメールマガジンにてお知らせいたします。
※資料は