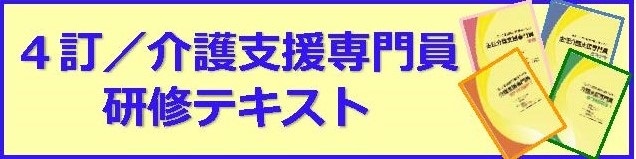9月5日、社会保障審議会介護給付費分科会(第79回)が開催されました。
今回の議題は、介護サービス利用者に対する医療提供のあり方と、
介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する基礎調査についてです。
介護サービス利用者に対する医療提供のあり方に関しては、
特別養護老人ホーム等における日常の健康管理、緊急時の対応、
配置医の果たす役割や、介護老人保健施設で提供される医療の範囲、
また、小規模多機能型居宅介護、グループホームでの看護提供のあり方など、
サービスごとの医療提供のあり方をどう考えるのかを主な論点として、議論が行われました。
また、医療機関以外での看取り対応への評価について議論が行われました。
後半は、「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する基礎調査」
(日本総合研究所)の調査結果中間報告が行われました。
ケアマネジメントの実態調査として、平成23年3月に厚労省の老健事業として実施されたものですが、
回収率の低さに、委員から「データとして使用できるものではない」などの意見が相次ぎ、
調査内容に関する議論には至りませんでした。
平成22年介護事業経営概況調査の有効回答率が12%だったことも踏まえ、
なぜケアマネジャーへの調査はこんなに回答率が低いのかという問いかけに対して、
厚労省側からは、調査期間が3月22日~3月31日までであったことなど、
東日本大震災の影響があること等が説明されました。
当協会の木村会長は、「概況調査は事業所に対して回答を求めているが、
協会は個人を会員とする組織であるため、オーナーはいると思うが全部は補足できていない」などの実態を述べ、
会員には調査回答への普及啓発を行っているものの、事業所への普及啓発の必要性も示唆しました。
また、調査実施にあたりケアマネジメントの成果が発現されるメカニズム(仮説)が立てられていることに触れ、
調査はケアマネジャーのおかれた環境からも分析することになっているので、
個人のスキルだけをもって語るのは避けるべきと強調しました。
本調査に関しては、整理をした上で改めて報告されることになりました。
また、この日は当協会の木村会長が、提言とは別に「ケアマネジメントをめぐる論点について」、同分科会で議論すべき項目出しをしています。
●議論の詳細は、メールマガジン169号で配信いたしました。
メールマガジンは、配信翌日から会員専用ページに掲載いたします。