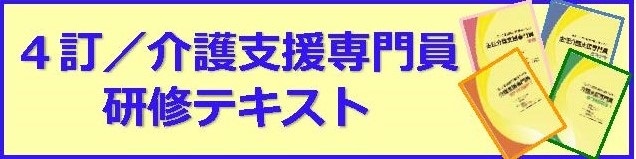日本介護支援専門員協会
会 長 木村 隆次
新年あけましておめでとうございます。
平成23年を迎えるにあたり、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
本年は、介護保険法改正と、平成24年4月介護報酬・診療報酬の同時改定を控え、日本の社会保障制度が大きな局面を迎える年になります。公的保険として税と保険料が投入されている介護保険サービスの単価(介護報酬)は3年ごとに、医療保険サービスの単価(診療報酬)は2年ごとに改定が行われています。平成24年度は6年に1度の同時改定にあたるため、制度間の継ぎ目をなくし、医療と介護を上手く連携して、効率的で有効的なサービスを提供するための改革が期待されています。
これに先立ち、昨年は厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会で介護保険法の見直しに向けた議論が集中的に行われました。法改正は、厚生労働大臣からの諮問を受け、その答申が告示に直結する報酬改定とは異なり、国会で改正法案を可決・成立する必要があります。したがって、それを踏まえたスケジュールで議論が進められ、昨年11月30日に「介護保険制度の見直しに関する意見」(報告書)が公表されました。
介護保険部会では、65歳以上の人が平成24年度から支払う介護保険料は月平均5,000円を超えることが必至の情勢だと示された上で、いわゆる財源論から発したことで、保険料上昇の抑制策の一つとして、居宅介護支援費(ケアプラン作成)等の利用者負担導入が論点としてあげられました。そもそも、日本の介護保険制度には「自立支援」の理念があり、それを行うためにケアマネジメントが導入されています。このケアマネジメントは、制度の根幹をなすものであり、要介護者・要支援者の誰もが公平に受けることができるように、利用者負担は0割(負担なし)で、この費用は全額を保険による10割給付の仕組みで運営されていることなどを踏まえ、私共は居宅介護支援費の利用者負担導入には断固反対する運動を行ってきました。とても厳しい戦いでしたが、結果として細川厚生労働大臣は12月24日の記者会見で、介護保険法改正案には利用者負担導入を盛り込まないことを正式に発表されました。
国の財源にも限りがあります。しかし、私たちケアマネジャーは、利用者の皆様が1ヵ月に負担できるお金にも限りがあることを十分承知しています。利用者負担が導入されれば、やむを得ず必要なサービスを削らざるを得ない事態が起こることは目に見えています。それにより状態が重度化し、かえって介護給付費の増大を招くことになれば、何のための財源論か本末転倒の話しになってしまいます。一方で、ケアプランは自分で作成することも可能ですが、全国的にみて毎月チェックをする市町村の体制が整っているとは言い難い状況です。また、居宅介護支援以外の介護事業者がケアプラン作成代行をする場合はサービス担当者会議の義務づけはありません。
ではなぜ、ケアマネジャーが担う居宅介護支援にはサービス担当者会議が義務づけられているのでしょうか。それは多職種協働によるケアマネジメントを実現するためにほかなりません。どの要介護度の人でも、ご本人ができることは必ずあります。それを見つけ出し、関係する皆で合議し、目標に向かって進むこと、そして尊厳のある生活を支援することが、本来のケアマネジメントであり、ここには利用者ご本人やご家族、介護保険サービス、さらに介護保険給付外のインフォーマルサービスなど、専門職としてケアマネジャーが見極めた地域のあらゆる資源が含まれているのです。
利用者の皆様からみれば、医療も介護も線引きはなく、全てが暮らしの一部ですので、本年行われる報酬改定の議論では、同時改定時ならではの隙間を埋める改革を行いたいと思っています。国民の皆様にとってよりよい制度を追求し、そのためにケアマネジャーはどうあるべきか、ケアマネジャーがおかれた環境をどうしていくべきか、これら1つ1つの課題に対して真摯に前向きに、現場のデータを揃えて取り組んでいきます。
地域包括ケアマネジメントの中心となる専門職として、国民の皆様が安心して住み慣れた地域で暮らすことができるよう、一層貢献していきたいと思います。
本年も皆様のご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
*************************************************************************
※会員(ケアマネジャー)の皆様への新年のご挨拶は、メールマガジンでお送りいたしました。
メールマガジンは、